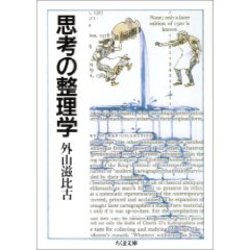
83年に刊行された本ながら、今年の秋に100万部を超えたと話題になっていた外山 滋比古氏の『思考の整理学』を読む。
書いてある内容の核は、ジェームス・ヤングの名著『アイデアのつくり方』とほぼ同じなのも興味深い。
やはり、「考える」「発想する」ということは、こういう事なんだなと納得する。
『思考の整理学』では、更に詳しく、分かりやすい喩えで、「(自分で)考える」ということをいろいろな角度から述べている。
印象に残る部分は多々あるけれど、VI章が特に印象深い。
この本は東大、京大生など大学生に多く読まれているということだけれど、この章は仕事をしている人たちにこそ響くのではないかな。
これまでは、”見るもの” ”読むもの”の思想が尊重されたから、”働くもの” ”感じるもの”の思想は価値がないときめつけられてきたのである。しかし、知識と思考は、見るものと読むものとの独占物ではない。額に汗して働くものもまた独自の思考を生み出すことを見のがしてはならない。いかに観念的な思考といえども、人間の考えることである以上、まったく、第一次の現実がかかわりをもっていないということはあり得ない。
それから、知的活動の三つの種類について。
これは自分の備忘録としてメモしておきたい。
①既知のことを再認する
②未知のことを理解する
③まったく新しい世界に挑戦する
外山氏はこれを読書にあてはめて、解説している。
人はしばし①の読書にとどまって、それを読書のすべてであるかのように錯覚してしまうという。
①に当てはまる本は読みやすいので、娯楽としての読書ということだろう。
読書が人間にとって、未知の世界への導入になりうるのは②の読書であると外山氏は云う。
これこそが知的活動という意味での読書の醍醐味だと思う。
私も読書量は多い方だと思うけれど、圧倒的に①の読書だ。
何となく分かってはいたけれど、こうやって指摘をされると少し意識的に②の読書量も増やそうかな、と思う。
そういえば、ベルギーのSEVENにすすめられたサイモン・シンの『暗号解読』を数日前から読み始めた。
これは、まさに②の読書。
なかなか面白いです。
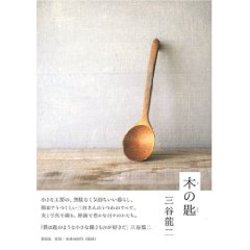
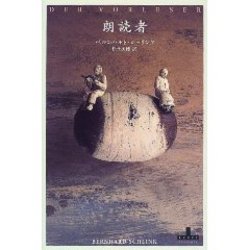
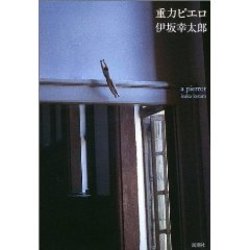
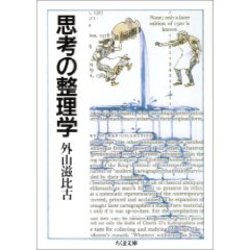
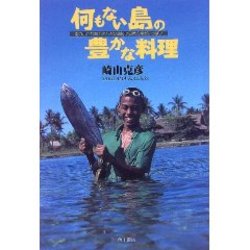

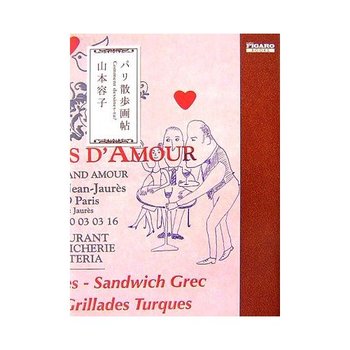
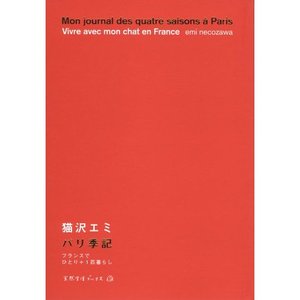
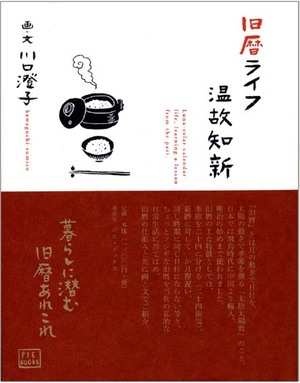


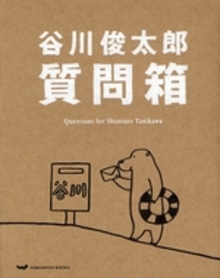
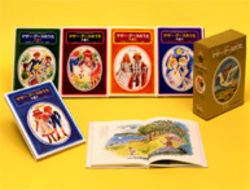
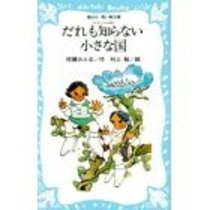
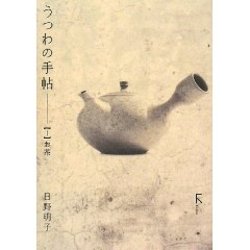

最近のコメント